小児科看護の分野では、子どもだけでなくその親御さんや家族も含めてケアが必要となることが特徴の一つに挙げられます。
家族の協力があってこそ看護ケアが実施されることもあり、家族とコミュニケーションをとりながら関係性を築いていくことはとても大切なことです。
今回は小児看護で家族と良好な関係性を築き、家族が安心して過ごすことができるように意識すべきポイントについてご紹介させていただきます。
まずは子どもとの関係性を大切に
子どもを知ること
家族と仲良くなる前にまずは子どもと仲良くなることが必要です。
子どもと仲良くなることで治療や看護がスムーズになり親御さんを安心させることにもつながるでしょう。
そのためには子どものことを知る姿勢が必要となるでしょう。
子どもの持ち物をリサーチしてどんなキャラクターが好きなのか、好きな遊びは何なのかなどを探ってみましょう。
子どもの好きなキャラクターの持ち物を持っていると関心を示してくれて仲良くなるきっかけになるかもしれません。
子どもの話を聞く
当たり前のようですが、子どもの話や訴えはきちんと聞くようにしましょう。
例えば、どうして嫌なのか?なぜ不安なのか?など。
理由や内容まで理解することでそれに対する対処ができ、子どものことをより理解した関わりから関係性を築きやすくなります。
子どもだからといった対応をするのではなく、1人の人間として関わりきちんと話を聞くことによって、徐々に気持ちを伝えてくれるようになります。
子どもでもプロセスのある説明をする
子どもだとつい軽い説明になってしまいがちですが、きちんと説明をしていくことが大切です。
例えば注射の時「大丈夫、痛くないよ〜」と軽くいったことが、
子どもにとっては「痛かった、嘘をつかれてた!」というようになりかねません。
このような場合は、「痛いけど頑張ろうね」と励ます関わりをしていくことが適切です。
子どもでも大人と同じように、事実とプロセスをきちんと説明しましょう。
小児科入院当初の家族のケア
子どもの入院が決まった時の家族の気持ち
入院当初は子どもの病状に対する不安があったり、付き添いで仕事の調整が必要であったりするなど家族自身の環境の変化に追われてしまうことも。
また、病状に気づくのが遅かったのは家族自身のせいではないかと自分に対しての自責の念を持ってしまうこともあり気持ちが不安定になりやすい状況です。
このような環境変化に対する労いと、不安の軽減のためのケアに努めることが看護師の役割としても重要になってきます。
「一緒に頑張っていきましょうね」などといった家族を支えられるような声掛けが良いでしょう。
丁寧な声掛けを心がける
ご本人はもちろん、家族に対してもまずは丁寧な声掛けを心がけていきます。
挨拶をすることはもちろんですが、その日のご本人の様子で良かった点を伝えたりするなどご家族が「この病院に入院して良かった」と安心できるような声掛けを行ないます。
家族からも情報収集を行う
家族からも患者さんの情報収集を行なっていくことを意識することで子どもと家族双方との関係性が築きやすくなります。
子どもの対応に困った場合にはどのように接しているのか尋ねたり、ケアをしていく上でどのような関わりを求めているのかの意向を汲み取ったりしましょう。
大切なことは、単に情報を聞くということではなく、それらの情報を得た上でケアに活かしていくということです。
今後の患者さんのケアに貢献することを意識した上で情報収集を行いましょう。
日常的な家族のケア
付き添いに関連したストレスに対する声掛け
点滴を受けたり、治療中泣き叫んだりと付き添いによって自分の子どもが苦しんでいる姿を付き添いのたびに見ることは家族にとってとても辛いものです。
また、繰り返される付き添いが生活の負担になってしまうことも。
こういった付き添いに関連したストレスを理解していくことも大切です。
「少しでもお力になれるよう私たちも頑張ります。」
「いつも○○ちゃんを支えていらっしゃる姿に私たちも励まされます。」
といったような労う声掛けで家族の負担をなるべく軽減できるように意識しましょう。
情報共有を大切にする
長期的なケアが必要となる場合には、家族と関わる機会も多くなってきます。
そのようなときでも良好な関係性を築きケアを継続していくための情報共有が欠かせません。
情報共有を円滑にするためにもこれまでの治療経過や看護記録をじっくり確認したり、週末の様子や記録を確認したりして気になる点があればご家族へ確認していきます。
「今日はご飯しっかり食べましたよ」
「昨日はこんだけよく眠れましたよ」
など、できる限り子どもが回復に近づくことができるような情報共有ができるとご家族としても安心材料となるでしょう。
家族自身のケアも行う
長期的なケアを行なっていく中で子どもに関したことだけでなく、家族自身をケアしていく視点も必要となるでしょう。
例えば、なかなか休息を取ることができていないご家族に対して、何気ない会話で和やかな雰囲気が作れるようにするといったことが挙げられます。
病室に来ることで家族が少しでも一息つけるような声掛けを意識しましょう。
また、看護師側の「がんばれ」というような励ましは帰って家族にストレスになってしまうこともあります。
そのため落ち込んだ気持ちや不安な気持ちを無理に励まさず、家族の立場を理解して寄り添っていく姿勢が大切です。
不安感が高い家族に対するケア
家族の不安の大きさを理解した声掛け
病状の変化や治療の先行きの見えない長期化に伴って家族の不安にも波があります。
子どもの病状や状況による家族の不安を理解することが大切です。
また表面上は気丈に振る舞っているように見えていても実際には大きな不安を抱えて過ごしているといった場合もあります。
病児ケアをしていく家族の立場に立って理解する姿勢を持ちましょう。
家族のその時の気持ちを理解し労っていく必要がありますが、全ての気持ちを看護師に伝えることが難しいということも踏まえて関わる必要があります。
無理に気持ちに深く入り込みすぎることなく、
「何かあれば声をかけてくださいね」といったスタンスで家族をサポートしていきたいという意向を見せ関わっていくことが大切です。
落ち着いた対応で寄り添う
家族が不安感の高い中、看護師には落ち着いていて安心できる関わりを求められます。
労いの気持ちを持ち、あたたかく接しながらも冷静さのある対応ができるように日頃から心がけておきましょう。
例えば、家族が看護師の子どもの関わりに対して細かく指摘する際に、
「ややこしい家族」と認識してしまいがちですが、子どもの病状や病院に対する不安の強さが影響している可能性もあります。
そういった家族でも立場に立って考え、安心できる声掛けや労いの言葉を伝えることで指摘が少なくなるかもしれません。
他職種で連携して支援していく
看護師は直接患者やその家族と関わる機会が多いためその様子をよく理解しているスタッフであると言えます。
普段の家族の様子や意向を共有して他職種で情報共有していくことは支援の中でとても重要な役割であるといえるでしょう。
主治医と相談しながら心理士によるメンタルケアに関するコンサルタントや、
ソーシャルワーカー経由で社会的サポートを活用するなど、
家族が必要な支援を受けられる架け橋となれるよう連携します。
必要に応じて家族を含めたカンファレンスの機会を持つよう他職種と連携をとりましょう。
カンファレンスの機会が定期的にあることで家族の安心材料の一つとなるでしょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回は小児科での家族のケアについて、それぞれの状況も踏まえてご紹介いたしました。
子どもとの関わりで臨機応変な対応が求められる小児科でご家族のケアまで行なっていくことが難しく感じることもあるかもしれません。
しかしご家族との関わりを大切にしていくことが治療をスムーズに進めていく上でとても大切になってきます。
家チカ!メディジョブでは、看護師の方に向けて臨床で役立つ情報を発信しています。
臨床で抱えるお悩み解決のヒントとなる情報がたくさん掲載されているので、ぜひご活用ください。

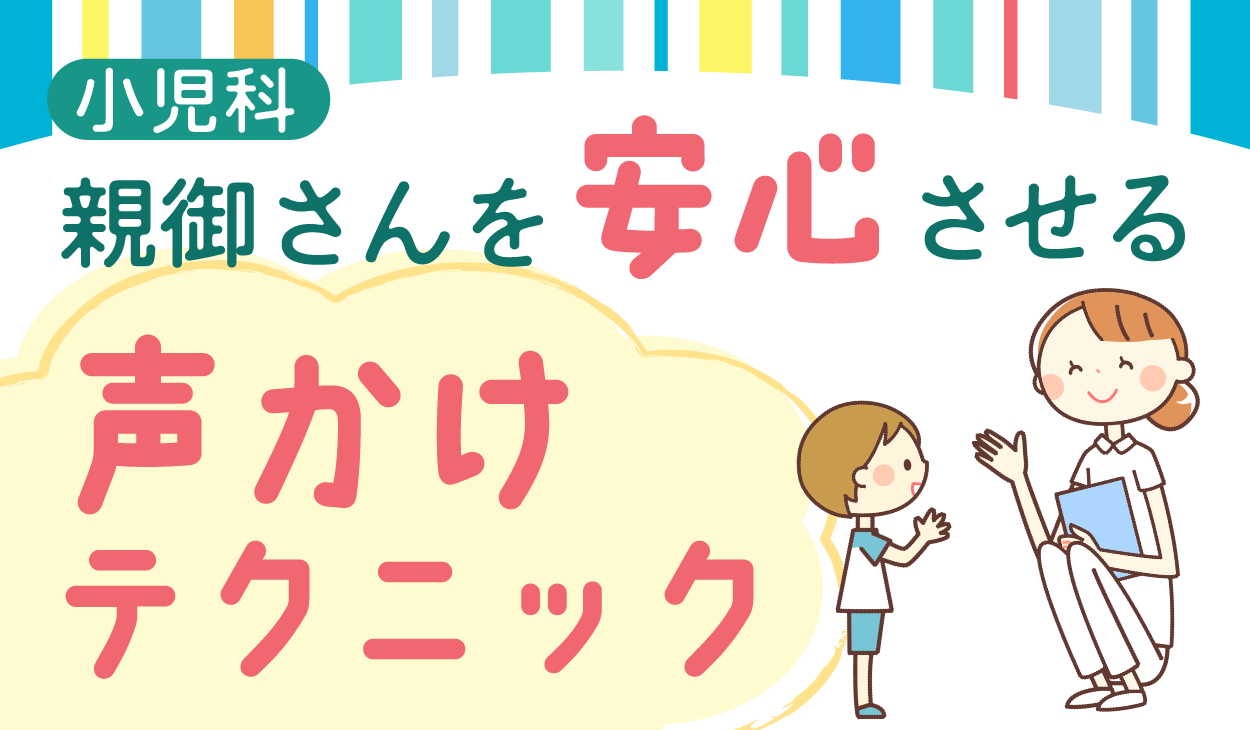

コメント